7月1日から平成29年度全国安全週間が始まります。
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で90回目を迎えます。
労働災害は長期的に減少し、平成28年の労働災害については、死亡災害は2年連続で1,000 人を下回る見込みとなっています。
しかしながら、休業4日以上の死傷災害(以下単に「死傷災害」という。)は前年より増加する見込みで、死亡災害についても平成28 年11 月から平成29年2月まで4か月連続で前年同月を上回っている状況です。
そこで、再度 安全対策の意識を高めるための今年のスローガンです。
・・・組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化・・・
by O
経済産業省は「日本再興戦略2016」に基づき、次世代ヘルスケア産業協議会健康投資ワーキンググループ(日本健康会議健康経営500社ワーキンググループ及び中小1万社健康宣言ワーキンググループも合同開催)において健康経営優良法人認定制度の設計を行ってきましたが、2月21日、認定制度を運営する日本健康会議において、2017年度の認定法人として、大規模法人部門(ホワイト500)235法人、中小規模法人部門95法人の認定を発表しました。
「健康経営」とは
従業員の健康保持増進の取組みが、将来的に収益性等を高める「投資」であるとの考えのもと、『健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること』です。
企業が健康経営の理念に基づき、従業員の健康保持・増進を行うことは、労災防止、生産性向上、企業イメージ向上等様々な効果に寄与するだけでなく、医療費適正化にもつながり、ひいては企業業績等の向上にも寄与するものと考えられます。
※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
By O
4月も、後半となりそろそろゴールデンウィーク の天気も気になります。晴天を願いたい時期ですが、統計によると 3月が台風1号の発生が最も多い月ということです。
気象庁では毎年1月1日以後、最も早く発生した台風を第1号とし、 以後台風の発生順に番号をつけています。なお、一度発生した台風が 衰えて「熱帯低気圧」になった後で再び発達して台風になった場合は 同じ番号を付けます。
台風には従来、米国が英語名(人名)を付けていましたが、北西太平洋 または南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政府間組織である 台風委員会(日本ほか14カ国等が加盟)は、平成12年(2000年)から、 北西太平洋または南シナ海の領域で発生する台風には同領域内で用いら れている固有の名前(加盟国などが提案した名前)を付けることになりました。
平成12年の台風第1号にカンボジアで「象」を意味する「ダムレイ」の名前 が付けられ、以後、発生順にあらかじめ用意された140個の名前を順番に用 いて、その後再び「ダムレイ」に戻ります。台風の年間発生数の平年値は 25.6個ですので、おおむね5年間で台風の名前が一巡することになります。
なお、台風の名前は繰り返して使用されますが、大きな災害をもたらした 台風などは、台風委員会加盟国からの要請を受けて、その名前を以後の台風に 使用しないように変更することがあります。また、発達した熱帯低気圧が東経 180度より東などの領域から北西太平洋または南シナ海の領域に移動して台風 になった場合には、各領域を担当する気象機関によって既に付けられた名前を 継続して使用します。 出典:気象庁ホームページ(http://www.jma.go.jp) by O
東日本大震災の発生から5年たちます。
大規模地震発生時には通信回線が規制され、被災者およびその親族等の居場所の確認や安否情報の共有が困難となることがあります。
そのような大規模災害発生時に、被災地への通話がつながりにくい状況になった場合、NTTの災害用伝言ダイヤル(171)、災害用伝言板(WEB171)のサービスが利用できます。
提供の開始、登録できる電話番号、伝言録音時間や伝言保存期間など運用方法・提供条件については、状況に応じて設定され、テレビ・ラジオ・公式ホームページ等を通じて周知されます。
また、このサービスは、災害発生に備えて毎月1日15日の他、年間に数日、体験利用できる機会も設定されています。万が一に備え、使い方に慣れておくのもいいかも知れません。
電話番号の覚え方は、・・・「いない(171)かな」・・・ です。
by O
 昨年7月、バングラデシュのダッカ市内のレストランにおいて、武装グループが 日本人7名を含む約20 名を殺害、多数が負傷する事件が発生しました。
昨年7月、バングラデシュのダッカ市内のレストランにおいて、武装グループが 日本人7名を含む約20 名を殺害、多数が負傷する事件が発生しました。
これを受け外務省は9月「中堅・中小企業海外安全対策ネットワーク」の第1回本会合を開催。これは安全対策に関する情報に接する機会が限られる海外での中堅・中小企業の安全対策を強化することを目的です。日本企業の海外展開に関係する15の参加組織・団体には、外務省、経済産業省、中小企業庁のほか、日本商工会議所、ジェトロ、中小企業基盤整備機構、国際協力機構(JICA)などがあります。
<海外安全対策に関する支援を強化>
特に、ジェトロでは、海外見本市への出品支援の際に、出品者マニュアルにおいて「万が一、テロが発生したときの行動」として、見本市会場内外での安全対策に関する情報を提供しています。
また、海外展開を目指す中堅・中小企業を支援する枠組みとして、新輸出大国コンソーシアム事業においても、国内外で安全対策に関する情報提供を実施。日本国内において、海外での事業展開に当たり必要となる安全情報を専門家(エキスパート)が提供するほか、情報ニーズが高い国・地域に所在する海外事務所を通じて、現地の安全対策に関して一層の情報提供を図っています。
by O
 2016年は、年末に一度の火災で約150棟を焼失するという大規模な災害に見舞われました。
2016年は、年末に一度の火災で約150棟を焼失するという大規模な災害に見舞われました。
年が明けて2017年、火災保険を見直すにはいいタイミングです。
消防白書によると、さかのぼって2015年度中に発生した火災は、次の通りです。
出火総件数 39,111件
【出火原因の上位】 1) 放火(疑い含む) 6,502件(16.6%)
2) たばこ 3,638件( 9.3%)
3) こんろ 3,497件( 8.9%)
⇒ また、建物だけに限ると
出火件数 22,197件
類焼棟数 31,780件(出火2件当たり約3棟が被災)⇒所謂「もらい火」
今回の大火もそうですが、火災の原因は自分以外にもあることがわかります。
火災保険にはきっちりと加入をしておいたほうがよさそうです。
by O
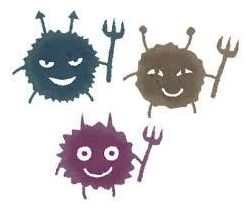 今期の冬は、ノロウィルスによる食中毒が大流行すると言われています。
今期の冬は、ノロウィルスによる食中毒が大流行すると言われています。東京都健康安全研究センターでは、11月24日にひとくち情報を発表しています。
2015-16シーズン ウイルス型別検出割合 計57件
ノロウイルス GⅠ
8.8%
ノロウイルス GⅡ
70.2%
ロタウイルス
12.3%
サポウイルス
8.8 %
1 感染性胃腸炎とは
感染性胃腸炎とは、主にウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。原因となるウイルスには「ノロウイルス」「サポウイルス」「ロタウイルス」「アデノウイルス」などがあり、主な症状は腹痛、下痢、おう吐、発熱です。
2 季節的に流行します
感染性胃腸炎は、例年、10月から増加し、12月頃をピークとして3月まで多発します。感染性胃腸炎の原因として最も多いものがノロウイルスです。
カキなどの二枚貝がノロウイルスを取り込んで蓄積し、これを生あるいは加熱不十分なまま食べて感染するほか、ノロウイルスに感染した調理従事者が汚染源と考えられる事例が多数確認されています。
また、食品以外の感染経路による大規模な集団感染も発生することがあります。
3 予防のポイント
どのウイルスであっても予防のポイントは変わりません。
• こまめな手洗いを習慣づけましょう。特に排便後、調理や食事の前
には、その都度、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
• おう吐物やふん便を処理する時は、使い捨ての手袋、マスク、エプロンを着用し、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系の漂白剤)で処理しましょう。処理をした後は石けんと流水で十分に手を洗いましょう(施設では処理用具のセットを予め準備しておきましょう)。
• ノロウイルスはカキなどの二枚貝に潜んでいることがあります。調理する際は、中心部まで十分に加熱しましょう(中心温度85~90℃で少なくとも90秒間の加熱が必要です)。
by O
 紅葉もすすみ、バーべキューなどで家族や仲間とお肉を食べる機会が多い季節になりました。
紅葉もすすみ、バーべキューなどで家族や仲間とお肉を食べる機会が多い季節になりました。
厚生労働省ではお肉による食中毒に関しての注意を呼びかけています。
―私たちの手の平や食べ物等には、様々な種類の細菌やウイルスが存在しています。
なかでも、牛、豚などの家畜の腸内には、食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌などの食中毒菌が存在し、と畜場でお肉にする過程で、お肉やレバーに付着してしまうことがあるため、生で食べるのは食中毒のリスクを伴います。
また、豚やイノシシの多くは、E型肝炎ウイルスに感染していることがわかっています。このウイルスは、豚の血液や肝臓からも見つかっており、生で食べることで人にも感染し、肝炎を発症し重症化することがあります。
また、寄生虫についても注意が必要です。
細菌やウイルス、寄生虫は熱により死滅するので、加熱により食中毒を防ぐことができます。このような病原体は、お肉やレバーの内部まで入り込んでいることがあるので、中心部まで火を通すことが大切です。内部まで、白っぽく色が変化したことを目安にしてください。
また、お肉を焼く際に使用する箸やトング、調理する方の手などには、生のお肉から病原体が付いてしまいます。
生肉を取り扱う箸などは専用のものを使い、食べる際には、必ず別の清潔な箸を使いましょう。
また、生のお肉を触った後は、しっかりと手を洗いましょう。
特に、バーベキューは、火加減が難しく、生焼けになることが多いことや保存温度が高くなりやすいことに加えて、箸などの器具の使い分けや洗浄が不十分になりやすいので注意しましょう。―
※家庭で調理をする場合、お肉を調理した包丁やまな板は、二次汚染を防止するため、きれいに洗い熱湯をかけましょう。 by O
この季節、運動をしてダイエットしたいという方も結構いると思います。
まず手始めにジョギングを始めるかたが多いようです。
では走った結果、どのくらいのカロリーを消費できるのでしょうか?
消費カロリーは、
“体重(キログラム)×走った距離=消費カロリー”
で、求めることができます。
例を挙げると、体重60キロの方が5キロの距離をジョギングしたら、300キロカロリーの消費です。
また、同じ方がフルマラソンを走ったとしたら、2531.7キロカロリーの消費です。
この2500カロリーもの数字は、成人男性の一日あたりのエネルギー所要量に相当します。
それだけフルマラソンは体力を使うことなのです。
走るには体脂肪をエネルギーとしますが、
体脂肪は1グラムで、7キロカロリーのエネルギーを持っています。
そこで先ほどの、フルマラソンで2531.7キロカロリー消費という数字を使います。
(2531.7÷7=361.67・・)
つまり、60キロの体重の方がフルマラソンをした場合、体脂肪は361グラムしか燃焼されてないのです。
フルマラソンに一回出場するよりは、日頃からこつこつ走るほうがダイエットにはいいようです。
by O
 今日から全国労働衛生週間の準備期間が始まった。以下のように要綱が発表されている。
今日から全国労働衛生週間の準備期間が始まった。以下のように要綱が発表されている。
これは、昭和25年の第1回実施以来、今年で第67回を迎える。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。
労働者の健康を巡る状況を見ると、平成27年度の脳・心臓疾患の労災支給決定件数が251人、精神障害の労災支給決定件数が472人となっていること、勤務問題を原因・動機の一つとしている自殺者が約2,200人いること、近年我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていることなど、職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対策は重要な課題となっている。
また、業務上疾病の被災者は長期的に減少し、平成27年は前年から47人減少して7,368人となった。疾病別では腰痛が74人減少したものの、4,550人と依然として全体の6割を超え、業種別では社会福祉施設が最も多くなっている。一方、熱中症については、前年から41人増加して464人となり、近年400~500人台で高止まりの状態にある。
さらに、化学物質による疾病は溶剤、薬品等による薬傷・やけど等が多く、また、特定化学物質障害予防規則等の対象となっていない化学物質を原因とするがんなどの遅発性の疾病による労災事案の発生等の新たな問題も生じている。
このような状況を踏まえ、平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法により、①ストレスチェック制度の創設によるメンタルヘルス対策のより一層の充実、②表示義務の対象となる化学物質の範囲の拡大と、一定の危険・有害な化学物質に対するリスクアセスメントの実施による化学物質管理、③職場における受動喫煙防止対策等を推進し、業務上疾病の発生を未然防止するための仕組みを充実させたところであり、その確実な履行が必要となっている。
また、平成26年11月に施行された過労死等防止対策推進法及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月閣議決定)に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援等の各対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することが求められている。
さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月閣議決定)に基づき、疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立支援対策が求められている。
このような背景を踏まえ、今年度は、
「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。
by O







