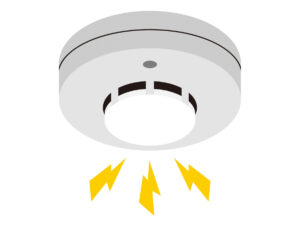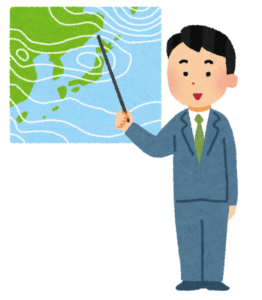師走に入り関東地方では最低気温が一桁台、空気も乾燥して寒い季節になりました。
この時期に気を付けたい、今回は火災についてのお話です。
火災死者の約7割は住宅で発生しています!令和元年中の住宅火災の件数は総出火件数の3割ですが、住宅火災による死者数は総死者数の約7割を占めています。
死者の発生した住宅火災の主な原因は、たばこ、ストーブ、コンロです。こららの火災を起こさないために「4つの習慣・6つの対策」を心がけましょう。
10のポイントはコチラ →→→ 住宅火災 いのちを守10のポイント
また、予防に大きな力を発揮してくれるのが「住宅用火災警報器」です。
住宅用火災警報器は、一般的には電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、その電池の寿命の目安は約10年とされています。
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器が適切に作動するよう、
火災予防運動の時期などに、定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。
参考:総務省消防庁HP
By:W
今年の立冬は11月7日。「立冬」とは、冬の気配を感じ始める日を指す言葉です。
秋の深さが増す時期でもあり、冬が近づいてきたと感じる人が多いでしょう。暖房器具が活躍する季節ですね。
そんな季節、、
地震が起きたとしても、いつもと同じように、何よりも自分の命を守ること、そしてけがをしないことが大切です。
緊急地震速報を受けたり、地震の揺れを感じたら、まず身の安全を最優先に行動しましょう。
火の始末は揺れが収まってから行いましょう。現在の都市ガスやプロパンガスは、震度5程度の揺れを感じると自動的にガスの供給を遮断するよう設定されています。
また、石油ストーブなどにも耐震自動消火装置を備えたものが普及しており、使用中の火気器具からの出火の危険性は低くなっています。
万が一出火した場合でも、落ちついて対応すれば、揺れが収まってからでも十分消火することができます。
暖房器具を出す際に上記のような安全機能が付いているか確認する事をおススメいたします。
☆東京消防庁がまとめた「地震その時10のポイント」↓↓↓がとても参考になります!是非ご覧ください。
→→→ 地震その時10のポイント
参考:東京消防庁HP
By:W
令和4年10月11日【エルニーニョ監視速報】が発表されました。発表によると「今後、冬にかけてラニーニャ現象が続く可能性が高く(90%)、その後、冬の終わりまでに平常の状態になる可能性もある(40%)が、ラニーニャ現象が続く可能性の方がより高い(60%)、と予測しています。」(本文抜粋)とのことです。
エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象はラニーニャ現象と呼ばれ、それぞれ数年おきに発生します。エルニーニョ現象やラニーニャ現象は、日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられています。
日本は、南米沿岸からもインドネシア近海の赤道地帯からも遠く離れていますが、これらの地域でラニーニャ現象が発生すると、日本にも大きな影響を及ぼします。
冬は西高東低の典型的な気圧配置となりますが、日本列島には偏西風の影響で北から寒気がさらに流れ込み、気温は下がり、大雪に見舞われる地域も各地で増えます。
今年も猛暑となり、ようやく暑さから解放されたとホッとするのも束の間・・備えあれば患いなし。余裕のある今だからこそ、冬の寒波・災害に備えましょう。
参考:気象庁HP
By:W
近年、大雨による土砂災害や浸水などが日本各地で発生しています。
今、どこで、どのくらい危ないのか?自分の周囲は安全なのか?危険が身に迫っている時、正しい情報を得ることは命を守るためにとても重要です。
気象庁では、大雨による災害の危険度の高まりを5段階の色分けで地図上に表示する「キキクル(危険度分布)」を公表しています。
地図上で視覚的に知ることができる情報で、気象庁のホームページで公開されています。
「キキクル」は、どの場所で、どのくらい災害の危険度が高まっているか、数時間先までの危険度をお知らせる情報です。
危険度の情報は10分ごとに更新されますので、こまめにチェックすることで、危険度の高まりを早めにキャッチすることができます。
スマートフォンのアプリやメールにリアルタイムで知らせてくれる「プッシュ型」の通知サービスもあります。
自主的な避難の判断に役立てることは勿論、離れて暮らす家族が住んでいる場所を登録しておけば家族に速やかな避難を呼びかけられます。
台風シーズンが到来しました。防災対策の一つとして、最新の正しい情報を得られる準備を備えましょう。
参考:政府広報オンライン
By W
誠に勝手ながら下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
◆夏季休業期間:8月15日(月)~8月19日(金)
8月22日(月)より、通常通り営業いたします。
※期間中の事故のご連絡は各保険会社の事故受付センターまでご連絡ください。
夏になると夏祭りや花火大会など多くの人が集まる催しがたくさん行われます。しかし、多くの人が集まる催しでひとたび火災が起きると、大きな被害につながるおそれがあります。
カセットこんろを覆うような鍋や鉄板を載せたり、こんろを並べて使わないでください。ボンベが過熱され破裂したり、周囲に置いてあるものに燃え移る可能性があります。
<注意のポイント>
■ カセットこんろは正しく使いましょう!
火気を使用している付近で廃棄のためガスボンベに穴を開けることはやめましょう。残っていたガスが噴出して引火するおそれがあります。
■ プロパンガスボンベのホースの差し込み、ボンベの固定はしっかりとしましょう!
ガス器具のホースはしっかりと差込み、安全バンドなどで締めましょう。ホースの差込みが足りないとガスが漏れて引火するおそれがあります。
また、ボンベが転倒するとガスが漏れる危険があります。安定した場所に置き、ブロックや紐でしっかり固定しましょう。
■ 火気器具や照明器具の周りは整理整頓しましょう!
器具の周りは整理整頓をし、ダンボールなどの燃えるものを近くに置いたりしないようにしてください。
また、ガス器具などは人の通る位置では使用しないでください。ホースをまたいだり、接触すると非常に危険です。
楽しい時間を過ごすためにも、火器器具の取り扱いには十分に注意をしましょう。
参考:東京消防庁HP
東京消防庁管内(稲城市と島しょ地区を除く)において、令和3年6月1日から4か月間に、
熱中症(熱中症疑い等を含)により3,414人が救急搬送されています。
例年、梅雨明け後の最初に気温が高温となる日に、急激に救急搬送人員が増加する傾向があります。
また、新型コロナウイルスの影響により、マスクの着用や自宅で過ごすことが多い生活となっています。
感染予防に配意し、熱中症予防対策をしましょう。
<<熱中症の予防対策>>——————————————————————————————————–
・暑さに身体を慣らしていく
・高温・多湿・直射日光を避ける
・水分補給は計画的、かつ、こまめにする
・ 運動時などは計画的な休憩をする
・乗用車等で子供やペットだけにしない
・子供は大人よりも高温環境にさらされています、子供の体調の変化に注意しましょう
—————————————————————————————————————————————–
暑さに身体を慣らする為に「ジワッと汗ばむ程度の運動」が有効だそうです。
運動をする時間を確保できない場合は日頃の通勤、買い物、散歩など、
いつもより少し早歩きを意識するといいですね。
また、本格的に夏が到来する前にエアコンが正常に稼働するか試運転をしましょう。
参考:東京消防庁HP
By W
災害の多い日本に於いて日頃の備えは大切です。最低3日分の食料の備蓄が必要だと聞いた事があると思います。
そこで、実際に備蓄用食品を食べてみました! 今回は第3弾として缶詰入り【チョコチップ マフィン】を試食してみました。
感想は独断と偏見、個人の感想ですw
《商品容器》 缶切り不要。簡単に開けることができる。
《開けてみた》想像より香は弱く油っぽい。
《食べてみた》‘しっとり’しているのでパサパサせず食べやすい。見た目よりチョコ感はないが程よい甘さ。二つ入りだが一つで小腹が満たされる。
《備蓄食品としてありか》 +アルファの予備として「あり」です。朝食やおやつ代わりに良いと思う。
・・・今回は第3弾としてマフィンをご紹介しました。缶詰なので比較的場所を選ばず保管ができるので便利です。
疲れると甘いものが欲しくなると思います。保存食に+アルファとしてあっても良いと思いました。

 by K
by K
台風の季節は未だ先のこと・・河原には菜の花が咲き誇り恐ろしい水害の記憶も薄れてしまいます。 いい季節だからこそ、冷静に必要な備えを見直す季節です!
・窓や雨戸はしっかりとカギがかけられるか?必要に応じて補強する
・ 側溝や排水口は掃除して水はけを良くしておく
・ 非常用品を確認しておく(懐中電灯、携帯用ラジオ(乾電池)、救急薬品、衣類、非常用食品、携帯ボンベ式コンロ、貴重品など)
・飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び込みに備えてカーテンやブラインドをおろしておく
・ 水を確保する(断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水を張るなどして生活用水を確保する。)
・ 避難場所を確認しておく
備品や設備のチェックは事前に備えることができますね。飛散防止フィルムなどは台風の接近が見込まれるとお店では完売が見込まれます。早めの準備は心に余裕がうまれます。是非、この良い季節に家族で我が家の備えを見直しましょう!
By W