「防災気象情報」とは、国や都道府県等が発表するもので、市町村等が避難情報の発令の判断を支援する役割と、住民が主体的に避難行動をとるための参考とする役割があります。
「警戒レベル」は、災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなります。住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとることが重要です。
【1】警戒レベル1は、災害への心構えを高める
【2】警戒レベル2は、ハザードマップなどで避難行動を確認
【3】警戒レベル3は、高齢者や要介護者等が危険な場所から避難
※土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いにお住まいの方も、準備が整い次第、この段階で避難することが強く望まれます。
【4】警戒レベル4は、対象地域住民の全員が危険な場所から避難
※対象地域で危険な場所にいる方は全員速やかに避難してください。
【5】警戒レベル5は、“命を守るための最善の行動を”
※すでに災害が発生・切迫している状況ですので、命を守る最善の行動をとってください。
近年ゲリラ豪雨で市街地では「内水氾濫」が起こりやすくなっています。短時間のうちに大雨が降り避難所などへ移動が難しい場合も想定されます。そのような時は「垂直避難」で身の安全を確保しましょう。 その為にも日ごろからハザードマップ、地域の地形や環境を把握して自分なりの避難経路を確認、自分が使いやすい災害用アプリをスマートフォンにダウンロードしておきましょう。
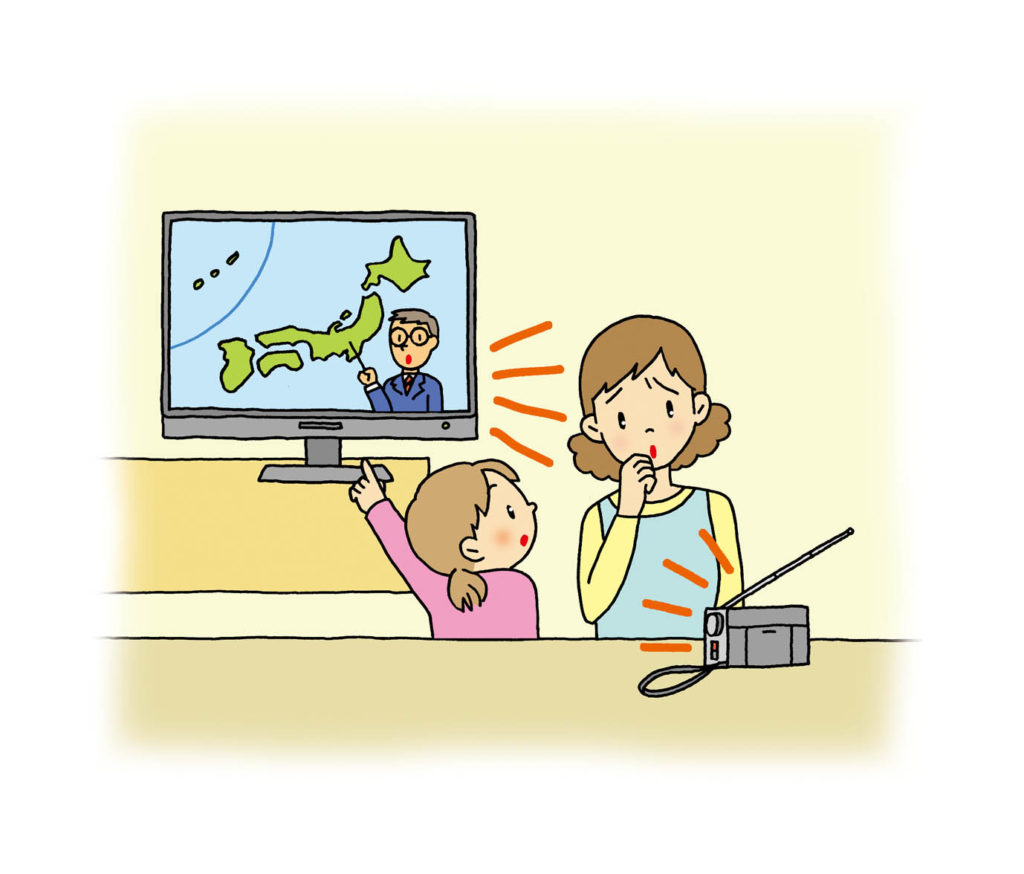
By W
参考:首相官邸HP
皆さんは万一の災害に備え、食品の備蓄をしていますか?
大きな災害が起きると、物流が止まり、スーパーやコンビニでも食品が手に入りにくくなります。しかし「備蓄」ときくと、何から始めたらいいのかわからなくて難しく感じるかもしれません。そこで、何をどれだけ、どういう方法で備蓄するのか。気軽に始められる食品備蓄のコツを紹介します。
************************************************************************************************************
~1~ なぜ、食品の家庭備蓄が必要なの?
大きな災害が発生すると、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなり、物流機能も止まり、1週間以上食品が手に入らない状況が想定されるためです。
~2~ 何をどれだけ備蓄すればいいの?
最低3日分、できれば1週間分。必需品は、水とカセットコンロ、カセットボンベ。缶詰やレトルト食品、カップめん、乾物など保存しやすい食品を備えましょう。
~3~ 食品の備蓄を始めるには?
まず普段食べているカップめんや缶詰、インスタント味噌汁など少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費し、食べたらその分を補充していく方法があります。
~4~ 乳幼児や高齢者、持病・アレルギーのある方は?
乳幼児や食べる力が弱い方、アレルギーのある方など配慮が必要な方には、その方に合った特殊食品の備蓄が必要です。災害時は手に入りにくいため、2週間分以上を備蓄しておきましょう。
************************************************************************************************************
災害はいつ起こるかわかりません。コロナ渦の災害ともなれば今まで以上に感染症対策にも注意を払った準備が必要です。 過剰な買い置きを控える為に「品目」と「賞味期限」のリストを作成すれば計画的に管理できますね!食品ロスを生まない工夫にもなります。
既に準備されている方は賞味期限の確認、未だ準備していない方は普段のお買い物のついでに少しずつ買い足してみてはいかがでしょうか?
By W

参考:内閣府大臣官房政府広報室
大雨で川を流れる水が急に増え、その水が堤防などを越えてあふれ出ることを「洪水」といいます。 洪水が起こると市街地では道路が水に浸かって交通がマヒし、家が水に浸かったり、崖くずれが起こったりといった被害は毎年のように起こっています。 国土交通省では、台風や集中豪雨が多い春から秋にかけてを出水期(しゅっすいき)として、洪水に対する備えを呼びかけています。
多くの市町村では【洪水ハザードマップ】を作成しており、水につかると予想される場所が深さごとに色分けして描かれ、避難所の位置や連絡先、消防署や警察署の場所、崖崩れなどに注意が必要な所などの情報が示されています。
身近な場所にどのような危険があるかを知ったら、家から避難場所までの行き方や、その途中にある危ないところ、急いで逃げることができそうな高い建物がどこにあるかも、併せて確認しておくと良いでしょう。 更には、身近な川にどのような危険がひそんでいるのか、実際に歩いて調べてみると、意識が高まります。例えば、橋げたなど見つけやすい場所には、「氾濫注意水位」や「避難判断水位」の表示がある場合があります。
良い季節になりました。コロナ疲れと言われる昨今、お散歩で気分転換がてら避難経路の確認や河川敷を観察しておくことは大切な「備え」となりますね。

参考:国土交通省カワナビ
By W
災害が発生した時、大切な家族の一員、ペットの安全確保についても普段から考え備えておく必要があります。避難するときは、ペットと一緒に避難(同行避難)できるよう、キャリーバックやケージに入ることなどに慣れさせておくことが必要です。日頃のしつけや健康管理はペットを守る大切な災害対策です。 また、ペットの安全確保の他にも気を付けたい事としてペットのストレスを軽減できる準備も必要でしょう。
現在ご自分が住んでいる地域で指定されている避難場所は、ペットとの同行避難が可能かどうかを確認し、ペットとの避難計画を考えておきましょう。避難所等においては、自治体の指示に従い、ルールを遵守しなくてはなりません。動物が苦手な方やアレルギーを持っている方等への特別な配慮が求められます。

最近、ペットにマイクロチップを挿入し迷子にならない対策が進んでいるそうです。マイクロチップを挿入した際は必ず(社公)日本獣医師会などに飼い主情報や動物情報を登録しましょう。 ペットは家族です。小さな命を守る義務を常に意識し災害に対する十分な備え、大切ですね。
参考:環境省HP
By W
日本は地震、火山活動が活発な環太平洋変動帯に位置し、世界の0.25%という少ない国土面積と比較して地震発生回数の割合は、全世界の18.5%と極めて高くなっています。
地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて政府と損害保険会社が共同で運営する地震災害専用の保険です。 火災保険とセットで契約する事ができます。地震保険の目的は損害を100%元通りにする事では無く、【地震等による被災者の生活の安定に寄与する事】とされています。その為設定できる保険金額も火災保険の30%から50%の範囲内(居住用建物は5000万円、家財は1000万円が限度)となっています。
地震保険の保険料は、「損害保険料算出機構」が毎年度検証を行い改定の必要があれば基本料率の改定を金融庁長官に届出し見直され、そこで決まった基本料率を元に地震保険料が算出されます。
今回、保険期間の開始日が2021年1月1日以降となる地震保険契約より改定が行われました。これは、2017年1月改定以降、3段階に分けて地震保険基本料率の改定を行うこととしていましたが、今回の改定はその3段階目となります。
東日本大震災から10年、様々な被害が発生した事は記憶に新しいです。日本に暮らす私たちにとって【地震】は身近な災害です。地震保険という国が関わり運営している制度を活用し、万が一被災したとしても、生活を安定する手立てを準備していれば不安要素が軽減されますね。また、ご承知の通り納税者は所得控除として【地震保険料控除】を受ける事ができるのもメリットの一つです。 地震保険に加入しているか?契約内容は? 日頃の災害対策と共に確認をお勧めいたします。
参考:首相官邸HP,金融庁HP,国税庁HP
By W
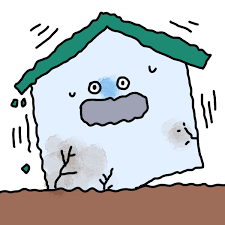
例年、この時期の関東地方は乾燥に悩まされますが、コロナ渦の今年はいつも以上に気になります。 内閣府HPには「スマートライフのために」というページがあります。《Withコロナ》で生活する為に心掛けたいポイントを動画やポスターで紹介しています。
この中ではマスクの着用やソーシャルディスタンス、3密、換気etc 既に国民に周知されている予防行動が紹介されていますが、加えて 《40%以上の保湿》 《こまめな拭き掃除》 も紹介されています。 保湿に関しては冬ならではの注意点ですね。
湿度は加湿器を利用、洗濯物を室内に干す、など身近なもので上げる事ができます。是非この時期は日ごろの感染症対策に+αで加え《40%以上の保湿》を心掛けましょう!
また、寒くなるこの季節は暖房器具を使用しますが火の取扱には十分に気を付けたいですね。
さて、二度目の緊急事態宣言が発出され飲食店の時短営業などが再び始まりました。私達はこの1年様々な報道で専門家の話を聞く機会に触れ、自然とコロナについて学んできました。 コロナ対策の大きなポイントは今更言うまでも無く【飛沫対策】。 様々な報道がありますが、大切なのは想像力を働かせ、判断・行動をする事。正しく恐れ、必要な感染症対策を怠らないことに尽きるのではないかと筆者は考えます。
By W
参考:内閣府HP
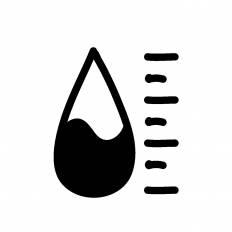
年内の営業は29日(火)正午までの営業となります。
年始は2021年1月6日(水)より平常通り営業致します。 尚、事故のご連絡は各保険会社の事故受付フリーダイアルへご連絡をお願い致します。
「持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)」とは,2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された【2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標】です。 17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。
「持続可能な開発目標」と、コトバだけを聞くと難しく感じます。 政府や大きな企業が先頭に立ち、一部の人が取り組んでいる・・そのような印象を抱く方は、少なからずいらっしゃると思われます。 筆者もその一人でした。 しかし、SDGsについて調べてみると、既に多くの方が当たり前の様に日々行っているチョットした行動が実は【SDGs】の取組みの一つになっている事を知り、とても身近に感じました。
例えば・・日本には昔から【もったいない文化】があります。今更ですが、素晴らしい文化ですよね。 食品ロスや無駄な消費を減らす、、省エネやゴミの分別もSDGsの取組みです。
小さな積み重ねが大きな力となる! 一人ひとりが今よりも う少し取組みを広げ強化していけば、5年後、10年後の未来は変わっているはずです (^o^)/*
今世界が抱えている問題は自然、エネルギー問題の他、差別や貧困問題など様々な問題が複雑に絡んでいます。SDGsはそれらの問題を総合的に取組む為、【世界を変えるための17の目標】を掲げています。 2016年日本は「SDGs推進本部」を設置し、SDGs関連に約4000億円を投資すると宣言しています。これら財源は国民の税金です。この側面から見ても他人事ではなく、自分の事として関心を持っていきたいと思います。
世界で起きている事を、自分の事として考える!
弊社もペーパレス、省エネに取組んでいます。微力ながら出来る事からコツコツ・・と(^^)
参考:外務省HP

By W
秋も深まり温かい食事が恋しい季節となりました。 スーパーの店先には【お鍋コーナー】が充実してきましたね。 そんな時、出番となるのが【カセットコンロ】。
さ~、久しぶりの出番に「ガス」の残量が気になりますが、今年は是非、【カセットコンロ】本体にも注目をしてください。 実はカセットコンロにも使用期限があるそうです。
一般社団法人日本ガス機器検査協会は10年を目安に買替を案内しています。
使用頻度が少なくても経年劣化によりガス漏れの危険が有る為です。
東日本大震災を機にカセットコンロを購入された方も多いと思われます。震災から10年。 買替の時期かも知れません。
カセットコンロは防災グッズとしても大変優秀です。しかし、ガス漏れを起こしては大変!大参事が起こる前に、安全確認をお願いします。
参考:一般社団法人日本ガス機器検査協会
By W

7月から10月にかけては日本に接近・上陸する台風が多くなり、人々の生活や生命が脅かされるような自然災害を度々発生させています。
大規模災害が発生した時、「公助」で全てを助ける事は難しく、「自助」が大変重要となります。「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動がとれるかがポイントです。
先ずは【ハザードマップ】で自分の家がどこにあるかを確認しましょう。 もし、家がある場所に色が塗られていたら、災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。
今年は新型コロナウィルス感染症が収束しない中での避難について、内閣府と消防庁が5つのポイントを示しているのでご紹介します。 大前提として【危険な場所にいる人は避難する事が原則】としていますので、それを踏まえて下記のポイントを確認してみましょう。
***********************************************************************************************************
1.安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません
2.避難先は安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう
3.マスク・消毒液・体温計は自ら携行しましょう
4.市町村が指定する避難場所、避難所は変更・増設されている可能性があります。災害時には市町村のホームページ等で確認しましょう
5.豪雨時の屋外移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認しましょう
***********************************************************************************************************正しい情報、早目の対策・行動は「災害」と「感染症」から大切な人を守ります。 避難に時間がかかる場合は【警戒レベル3】が出たら避難しましょう。
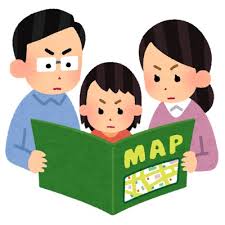
参考:内閣府
By W




